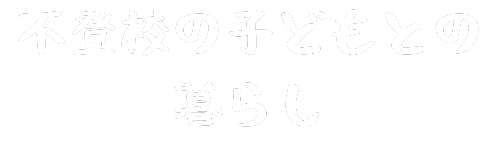不登校になってから、2回目の夏休みを迎えました。
子どもが学校に行っていたときは

昼ごはんもいるし、もう大変!!
早く夏休み終わって~
と思ってました。
なのに、不登校になってからは

あ~これでしばらく私も学校のことから離れられる!!
夏休みは気楽に過ごそう!
そんな風に変わりました。
そして、それは子どもたちも一緒でした(笑)
子どもも親も、学校から解放されるのが夏休みですね。
去年の夏休みはまだまだ子どもたちもパワーがなくて。
充電期間としてゆっくりすることにしましたが、月日をかけて徐々に元気になってきた子どもたち。

不登校になって2回目の
わが家の夏休みの過ごし方をお話したいと思います。
ご興味ある方はお付き合いください。
現状確認をする
まず、夏休みに入る前に
子どもたちの頑張っていることや取り組んでいることを確認しました。
ポイントは「夏休みに入る前」です。
夏休みに入ってしまったら、私も気が緩んでしまうからです(笑)
◎長男は↓
行けないときは家に来てもらう
(1時間/週1)
・民間フリースクールでの学習と活動
(2時間/週1)
・不登校専門家庭教師さんに来てもらい勉強
(1時間半/週1)
フリースクールは1か月前から通い始めました。
💡まずは新しい環境になれること
💡学習習慣の定着化(自宅学習含めて)
この2点を目標に取り組んでいます。
◎次男は↓
・英語学習をはじめる
💡1学期前半週1ペース⇒後半週3ペースに登校回数が増える
💡宿題に取り組む
💡英語学習に興味を持つようになる
気持ちがすごく前向きになり、頑張ろうと思えることが増えました。
夏休みの過ごし方を話し合う
現状確認したうえで、夏休みの過ごし方を一緒に考えました。
親子で描いている地図が違ったら、進む道もゴールもちぐはぐになりますよね?
☑親目線→「これが出来ていない」となり、つい言い過ぎてしまったり…
☑子ども目線→「頑張ってるのにまた怒られた」となったり…
過ごし方をすり合わせることで、余計な衝突を生まないように心がけています。
不登校になって2回目の夏休みの過ごし方
では、具体的にどのように夏休みを過ごすのか。
◎長男↓
①今頑張っている課題に継続して取り組む
1学年下の数学と理科を長男のペースで頑張っています。

長男自身が考えて、学習習慣がつきつつあります。
本人に任せ、親は引いて見守ろうと決めました。
②学校から配布された生活表を毎日書く
1学期終業式の日、担任の先生が家庭訪問に来てくれました。
「この夏は生活表を毎日書いてみようか」と先生から言われたことをきっかけに、この夏頑張ることのひとつにしたようです。
③朝自分で起きる(目標8時)
目覚まし時計は嫌だそうで、体内時計頼りで起きています(笑)
なかなか起きれず10時まで寝ていることもあるため、自分で起きるためにどうすればよいか模索中です。
長男自身が考えて行動することを大切に。
その結果転んだことも受け入れて、時には後退しつつも前に進んでほしいと思っています。
◎次男↓
①夏休みの宿題に加え、1学期中の学習課題で取りこぼしているところに取り組む
そのために、どの課題をどの程度、いつ取り組むのかスケジュール表を作りました。

やみくもに進むより、しっかりスケジュールを組んでおくことにしました。
②塾の体験に行ってみる
友達が通っている塾に興味をもったので、夏休みに体験に行くことにしました。
本人の意思があったので、チャレンジする良いチャンスだと感じました。
③オンライン英会話をする
英語に興味を持ったので、試しにオンライン英会話を体験しました。
楽しく学習していたので、夏休み中も不定期で受講することにしました。
前もって取り組む課題を洗い出し、一緒にスケジュールを決めるようにしました。
・取り組む課題は本人が決める
⇒自己決定する練習
・週1回何も勉強の予定を入れない日を作る
⇒体調不良などのイレギュラーなことが起こった時の予備日的役割
・状況に応じてスケジュールは変更できると次男に伝えておく
⇒臨機応変に対応する経験を積む
まずは子ども自身が元気になること
夏休みに入る前に現状確認をして、具体的な過ごし方を話し合い決めました。
長男・次男、個々取り組む内容も親の伴走具合も違います。
1年前、長男は勉強を全くしていませんでした。
外に出ることも今より少なかったです。
次男は夏休みの宿題に取り組むだけで精一杯でした。
そう考えると本当に本当に、勉強も勉強以外のことも、❝やってみよう❞と思える心の土壌が広がったと感じます。
土壌が弱っていては、いくら種まきしても芽は出てきませんよね?
不登校の状況や背景はみんなそれぞれ違います。
人と比べる必要はないし、まずは心の土壌を広げる=子ども自身が元気に過ごすことが一番だと思います。
さて約1か月後、夏休みが終了したときにどのような振り返りができるのか…
ちょっとドキドキしつつ、親の私も夏休みを楽しみたいと思います。

結果ブログもまた書きますね~!