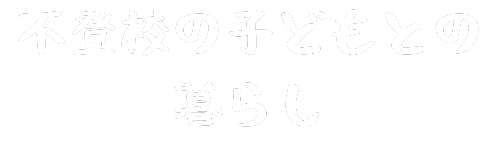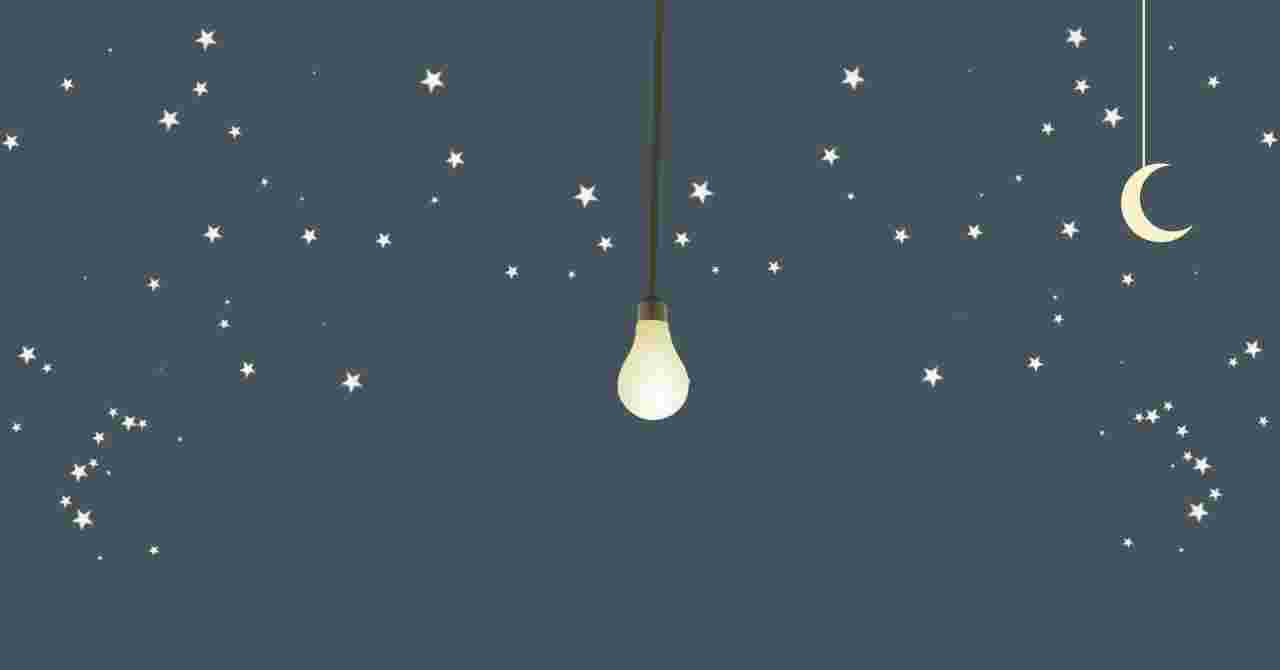あと10日ほどで夏休み明けですね。
長い夏休み。
親的には「ようやく明ける~!」というのが一般的な反応でしょうか。
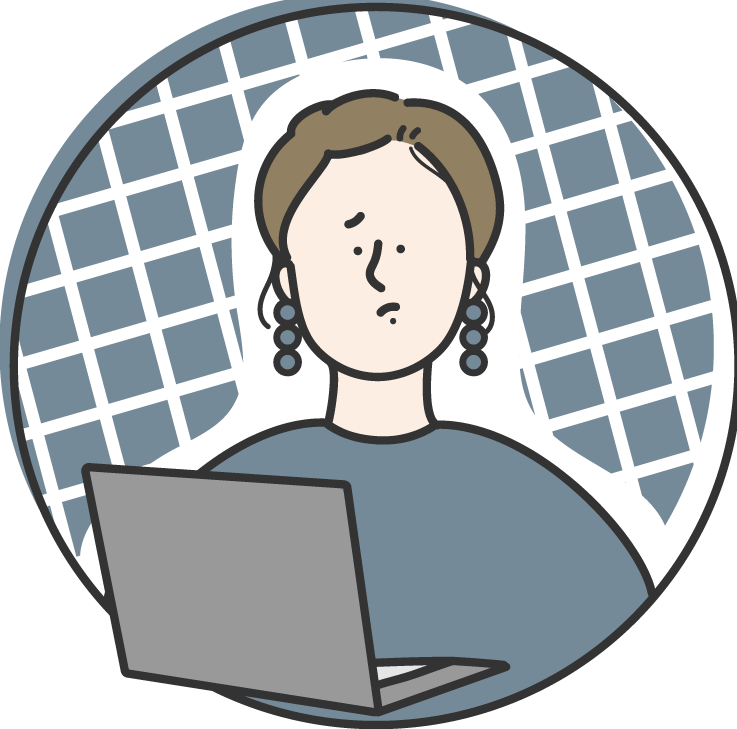
この時期になると、
思い出すことがあります。
それは、ちょうど2年前の夏休み。
長男は小6、次男は小4でした。
そして、この夏休み明けから長男の不登校生活は始まるのです。
…そんな2年前の長男のような気持ちの子どもがいるかもしれない
今回は不登校生活が始まる直前の夏休みの出来事をお話します。
長男の癇癪
2年前の夏休み。
あと1週間で終わるというのに、長男は宿題が終わっていませんでした。
私はまくしたてるように追い込んで…
最後の最後に残ったのは図工の平和ポスターでした。
画用紙や絵の具はあるのに、全然進みません。
もともと絵を描いたりすることに興味もなく得意でもない長男…
私も半分感情的に。
(いや、もはや感情むき出しだったかも…)
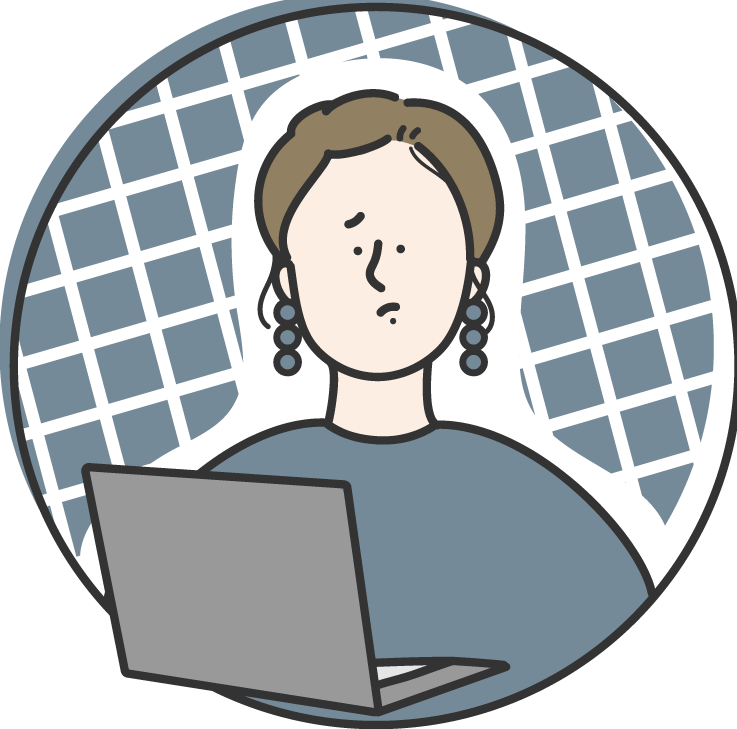
早く仕上げなさい!!
と言って怒ったり。
参考になりそうな構図やイラストを検索して提案したり。
なんとか完成させないと…と必死でした。
長男は荒れていました。
癇癪気味に暴れ、物は投げるし壁には穴を開けるし。
しかし、このような反応は初めてではありませんでした。
ストレスがかかると癇癪気味に暴れることは過去ありました。
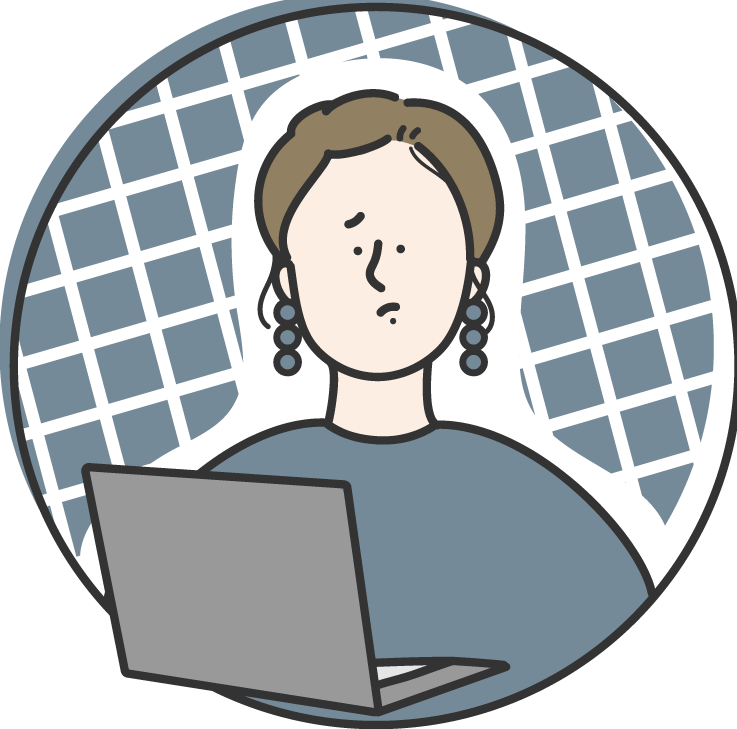
ああ…またか…
そんな気持ちでやりすごしていました。
次男の腹痛
長男の宿題の追い込みで大変な頃…
次男は夜中になると
(次男)
「お腹が痛い」
そう言って、1時間ほど布団の上でのたうち回りました。
普通のお腹の痛がり方ではなく、抱えるようにして唸る…
下痢や嘔吐などの随伴症状は一切ありません。
しかし、ひどいときには胸の方まで痛い…と。
もちろん総合病院の小児科を受診。
問診・採血・エコー検査など、一通りしてもらいました。
結果は異常なし。
整腸剤を処方してもらいました。
これは病的なことではない。
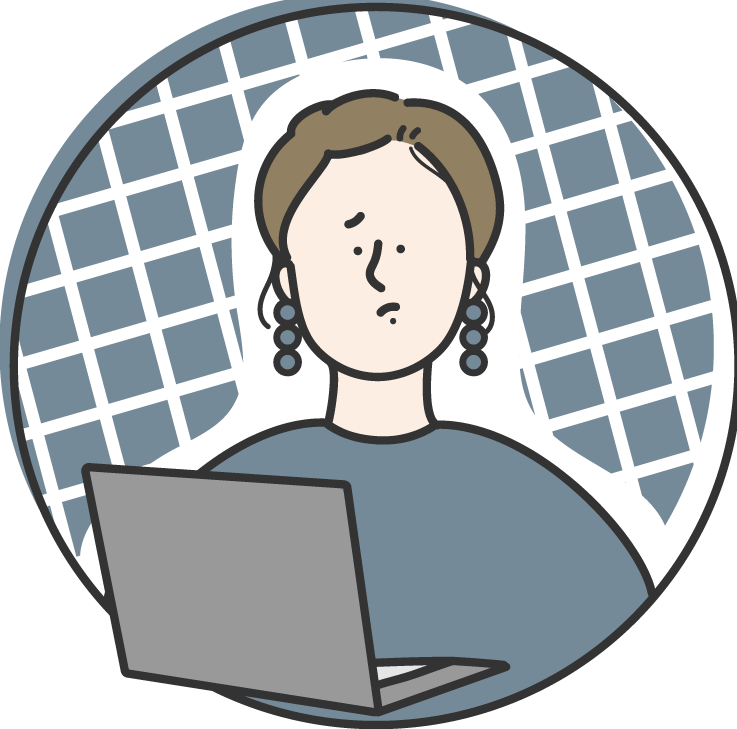
精神的なものがトリガーになってる??
安心すれば症状が落ち着くのではと思い、
処方された整腸剤を❝よく効く薬だよ❞と伝えて内服させました。
また、聴診器を実際にお腹に当てて、大丈夫であることを伝えました。
(私は医療職で、聴診器を持っていました)
数日間このようなことが続きましたが…
夏休み明け、ピタリとやみました。
夏休みはアンテナを高く張る
次男の腹痛は、おそらく長男の影響…
暴れたり物を投げたりしていたことが次男の精神的なストレスとなり、身体症状として出たんだと思います。
しかし、長男が悪いわけではありません。
長男が癇癪気味だったのは、学校に対する限界を迎えた気持ちが爆発したからです。
もうすぐで夏休みが明ける…
学校に行かないといけない…
今だから振り返りそう思えますが、当時の私には気付けませんでした。
この頃のことを長男に聞いても
「記憶がない。あんまり覚えてない。」
と言います。
きっと、本当に精神的に限界だったんだと思います。
学校にしんどさを抱えている子どもにとっては、
夏休み明けは一番ストレスがかかる時期と言われています。
もしも2年前に戻れるのなら…
癇癪を起こさざるを得ないほど追い詰められていることにフォーカスするべきだった…
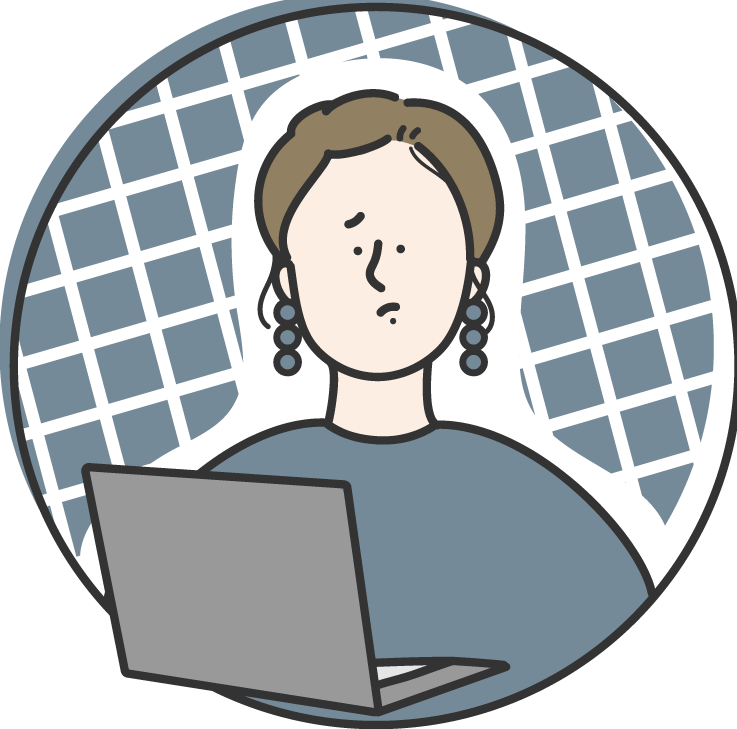
見えている事実だけしか
目を向けられてなかったのです
【夏休み明け 不登校】でネット検索するとこんな記事がありました⇩
夏休みが明けて学校が再開する時期は、子どもの自殺や悩み相談の件数が増える傾向があり、不登校の子どもの支援に取り組む東京 文京区のNPOの代表は「『学校に行きたくない』と子どもが伝えてきた場合は理由を聞くのではなく、まずはその気持ちを受け止めることが大切だ」と話しています。
引用元:夏休み明け 不安定になりやすい子どもとどう向き合うか | NHK | 教育
親からすると、まさか子どもがそこまで追い詰められている状況とは思わない。
まして、不登校になるなんて思っていないと思います。
2年前の私もそうでした。
夏休み中の子どもの様子には、いつも以上にアンテナを張って観察してほしいと思います。
心を守ること
長男は夏休み明けの始業式は登校しましたが、その翌日から不登校になりました。
しかし、自分の心を守った行動の結果が❝不登校❞という形だったと思います。
そうせざるを得ない限界がくる前に気付いて寄り添ってあげられていたら…
と後悔しています。
しかし、その時の私はその時で必死だったことも事実。

長男が自分の心をきちんと守れたことに
感謝しています。
もうすぐ夏休み明けです。
しんどさを抱える子どもたちが、少しでも救われますように。